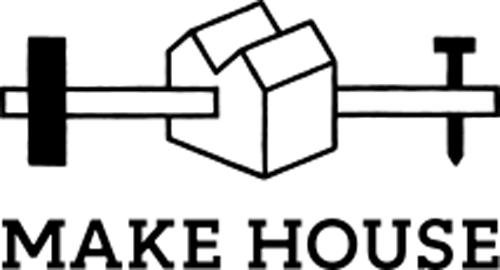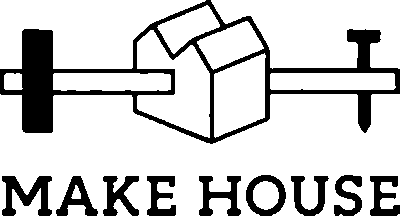建設業界は労働者不足などの問題を抱えているため、「今後10年・20年…という長期的な視点で将来性はあるのか」と不安を感じている方がいらっしゃると思います。
結論からお伝えすると、建設業界は今後10年もその先も、必須産業であり続けます。
ただし建設業界が大きく変化する動向も予測できるため、今回はBIMによって建設業務の最適化をサポートしている『株式会社MAKE HOUSE』が、建設業界の将来性をわかりやすく解説します。
建設業に従事している方・これから建設業界で働きたいとお考えの方が、今後も安定して仕事を確保し、力を発揮していく環境を構築するために、ぜひ最後までごらんください。
建設業務の最適化に役立つBIMにご興味をお持ちの方は、株式会社MAKE HOUSEへお問い合わせください。
Contents
建設業界の現状|2025年時点で「建設業界に未来はない」と言われる理由
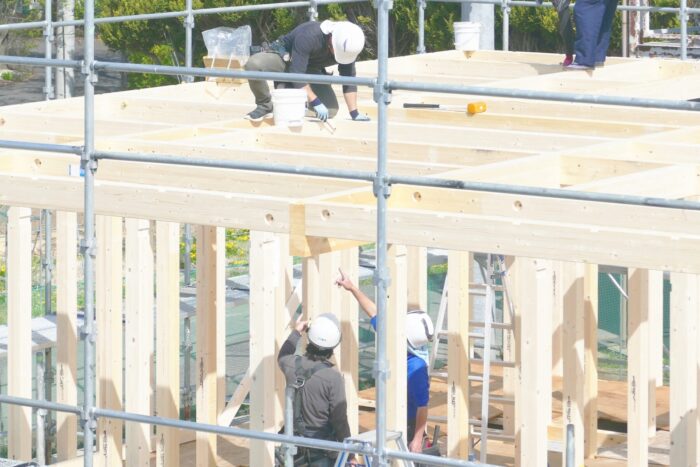
はじめに、建設業界の現状を簡単に確認しましょう。
2025年時点で、建設業界には主に労働者の状況に関する以下のような問題があり、SNSなどで「建設業界に未来はない」という意見に触れることもあります。
- 労働者減少:ピークの685万人(1997年)から減少し続け、2023年時点で483万人
- 労働者の高齢化:2023年時点で最も多い年齢層が50〜54歳で43%、29歳以下は11.6%
- 労働者の待遇:労働日数・労働時間が多い、下請け企業の賃金が低い など
〈参考〉国土交通省ウエブサイト『第25回基本問題小委員会 配布資料』資料1 建設業を巡る現状と課題
賃金については、世界情勢の影響で資材高騰が続く中、「上昇した原価率を工事請負額に転嫁できず、賃金が圧迫されている」という事情もあります。
ただし建設業界が社会の中で果たす役割は大きく、今後10年もその先も、建設業界は必須産業であり続けます。
また、国は建設業界の問題を解消するために、さまざまな取り組みを実施しています。
- 最低賃金引き上げ
- 賃金上昇につながるキャリアアップシステムを提供
- 公共工事で休日を考慮した工期を設定
- 時間外労働を規制
- 公共工事発注者などが適正な予定額を設定する体制の強化
- 工事発注者へ、工事請負契約を締結後に資材高騰などが起きた場合の請負額変更を受け入れるように要請 など
〈参考〉国土交通省ウエブサイト『第25回基本問題小委員会 配布資料』資料1 建設業を巡る現状と課題
次に、国が将来に向けて上記のような取り組みを強化している理由も紹介するので、参考にしていただけると幸いです。
建設業界が今後10年もその先も必須産業である5つの理由

「建設業界が今後10年もその先も必須産業である」と言える主な理由は、以下のとおりです。
- 建物などの新築・新設需要がなくなることはない
- 既存建物の保守管理需要がなくなることはない
- 建設業界は国全体のインフラ更新に必須の産業
- 建設業界は災害対応に必須の産業
- 国際社会の中でも日本の建設技術・技術者のノウハウは価値がある
それぞれ、今後10年・20年・30年と長期的な見通しがあるため、確認しましょう。
建物などの新築・新設需要がなくなることはない
建物などの新築・新設需要は多岐に渡り、需要がゼロになることはありません。
- 公共施設等の新築
- 道路・トンネルなどの新設
- 土地造成
- 堤防などの工作物の新設
- 民間事業所や商業施設の新築
- 住宅の新築 など
ただし日本は人口減少が顕著な状況で、建物の中で最も新築棟数の多い「住宅」の発注者となる主な年齢層の人口(65歳未満)が、2040年までに大きく減少していきます。
他の建物などについても、人口減少にともなって国全体の新築・新設件数が減少していくことは明らかですよね。
そのため今後10〜20年間で、建設業界の中では「安定しやすい企業」「安定しづらい企業」が2極化していくことを想定できます。
※のちほど、建設業界の企業経営の将来性予測を「建設業界の企業経営の将来性|今後10年で2極化する」で解説します。
既存建物などの保守管理需要がなくなることはない

日本の既存建物は以下のような状況で、今後10年で建物などの保守管理需要が高まっていくことを想定できます。
【例(2025年時点)】
- 住宅:リフォームなどのメンテナンスが必要となる築20年以上の住宅が約64%
- 学校:築40年以上が50%以上で、そのうち改修が必要な学校は約70% など
〈参考〉
・住宅:政府統計の総合窓口(e-Stat)『令和5年住宅・土地統計調査』>5-2住宅の所有の関係(6区分)、建築の時期(9区分)別住宅数ー全国、都道府県、市区
・学校:文部科学省ホームページ>トップページの検索窓に「学校施設整備を取り巻く現状等」と入力して検索>令和7年1月27日公表資料
建設業界は国全体のインフラ更新に必須の産業
国内のインフラは老朽化が深刻な状況で、早急に現状を更新するべき設備・施設などが、今後10年・20年でさらに増加していきます。
※インフラとは、道路・鉄道・電気・ガス・水道などの、生活に必須の設備・施設などのことです。
〈参考〉国土交通省ウエブサイト『社会資本の老朽化の現状と将来』
国は「インフラ関連の事故発生後に対応する費用」よりも、「事故の予防費用」の方が費用を抑えられるという試算を完了していて、インフラ整備を支援していく方針です。
〈参考〉国土交通省ウエブサイト『国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画)』
建設業界は災害対応に必須の産業

建設業界は、災害対応の最前線で活躍する産業でもあります。
日本ではさまざまな災害が予測されていて、災害後には長期に渡って建設業界の需要が増加します。
【過去の災害の復興期間】
- 1995年 阪神淡路大震災:約28年で復興事業完了
- 2011年 東日本大震災:約9年でインフラ整備などの大半が完了
- 2024年 能登半島地震:復旧・復興未完了で、河川整備については2029年までの計画がある など
〈参考〉
・阪神淡路大震災:国土交通省ウエブサイト『阪神・淡路大震災からの復興と東日本大震災』
・東日本大震災:国土交通省ウエブサイト『東日本大震災からの復旧・復興に向けた取り組み』>東日野大震災への10年間の対応と今後の取組(令和3年3月9日)
・能登半島地震:国土交通省ウエブサイト『令和6年能登半島地震からの復旧・復興状況と今後の身通し(令和7年出水期前時点)』>報道発表資料
今後も「南海トラフ地震」「首都直下地震」「日本海溝・千島周辺海溝型地震」などが予測されているほか、水害・火山災害・雪害などは毎年発生していて、建設業界は常に減災対策のための需要も担っています。
国際社会の中でも日本の建設技術・技術者のノウハウは価値がある
日本の建設技術・技術者の持つノウハウは国際的な評価が高く、多数の建設業者が世界各地でインフラ整備・都市づくりなどを手掛けています。
そのため、国内需要の減少に伴って、地域を広げて需要を確保することも可能です。
【例】
小規模の建設業者も、海外に建設技術などを提供しています。
- 従業員数25名の建設業者が、ベトナムを拠点としてトンネル制御システム等を提供
- 従業員数15名の建設業者が、台湾などへ地盤沈下復元修正工事を提供 など
〈参考〉国土交通省ウエブサイト『中堅・中小建設企業の海外展開支援について』>建設技術集(日本語版)
「建設業界が今後10年もその先も必須産業である」と言える主な理由を紹介してきました。
建設業界の動向を確認したことで、「求められる人材像・企業像のイメージ」が湧いてきた方も多いのではないでしょうか。
次に、建設業界で今後10年・20年と長期的に求められる人材像・企業像をまとめて紹介します。
建設業界で今後10年以降も求められる人材像・企業像

建設業界で今後も長期的に求められる人材像・企業像は、以下のとおりです。
- デジタルツール導入に対応できる
- 熟練工のノウハウを吸収できる
- 専門分野と関連する分野にも興味を持ち、広い視野で連携できる
- 災害対応など緊急時に的確な対応ができるよう、専門性を高める努力を継続できる
- 組織を管理できる(人的管理・財務管理など)
- 海外対応ができる
〈参考〉国土交通省ウエブサイト>トップページの検索窓に『人材育成について』と入力して検索
万能な人材を確保するのは難しいのが現実ですが、特にノウハウを蓄積できる若年層の労働者増加を目指して、国が指針などを発信しています。
建設業界の将来性予測|今後10年の労働環境・技術革新・企業経営などの動向

最後に、建設業界の現状や現時点で決定している国の施策などを踏まえて、建設業界の今後10年の具体的な将来性予測をお伝えします。
- 労働環境の将来性
- 技術革新の将来性
- 企業経営の将来性
- 建設業界の中で今後10年で需要が高まる&安定し続ける業種
建設業界の労働環境の将来性|今後10年で改善する見込み
国・業界団体が連携して建設業界の賃上げ対策・働き方改革に取り組んでいるため、建設業界の労働環境は今後10年で改善する見込みです。
【働き方改革の代表例】
2024年4月より、建設業の働き方に「残業は原則、月45時間以内・年360時間以内」という規制を適用
実際に、公共工事の積算に組み込まれる賃金は、2012年以降から上昇し続けています。
また、政府は建設業界の労働者不足を解消するために、女性活躍の拡大に取り組んでいます。
※2014年から2024年の10年間で、女性技術者が2.3倍になりました。
今後は女性が働きやすい環境整備をするほか、力仕事などの軽減に役立つ設備導入なども強化する方針で、建設業界全体の労働環境が改善されていきます。
建設業界の技術革新の将来性|今後10年で急進する

国土交通省は、2024年から「5年間」「6〜10年間」「11〜15年間」と期間を分けて、「建設現場のオートメーション化ロードマップ」を作成済みです。
【例】
- BIM※/CIM原則化
- AIを活用した施工計画策定
- 施工のオートメーション化(1人が複数の機械を操作)
- 遠隔操作機械の普及 など
〈参考〉国土交通省ウエブサイト『「i-Construction2.0」を策定しました』>i-Construction2.0 〜建設現場のオートメーション化〜
※BIMは建設業務の最適化に役立つシステムで、こちらの記事でBIM原則化の具体的な内容を確認できます。
▶おすすめコラム:BIMで建築確認申請|2025・2026年の導入ポイントと義務化、提出物・手順について
今後10年間で、民間にも徐々に新技術活用が広がると想定できます。
こちらの記事で、民間の建設業者が施工の合理化に取り組む具体的な方法も確認できます。
▶おすすめコラム:「施工の合理化に役立つVEとは|中小建築業者が健全なコスト削減&工期短縮を目指す具体的な方法を簡単解説」
建設業界の企業経営の将来性|今後10年で2極化する

建設業者数の動向は以下のとおりで、今後10年間で市場規模と比例して建設業者も減少していくことを予測できます。
- 創業数:10年前と比較して微減。減少傾向が継続する見込み
- 廃業数:社会情勢の影響で数値が乱高下するが、減少傾向。創業数よりも少ない
- 建設業許可取得数:2017年から増加が継続
〈参考〉国土交通省ウエブサイト『全国の建設業許可業者は2年連続で増加〜令和6年度末の建設業許可業者数調査の結果〜』
また、建設業許可数の動向を確認すると、今後10年で「経営母体が大きい企業ほど工事を請け負いやすい状況が加速する」という状況も予測できます。
【建設業許可数の動向(2000年と比較)】
- 個人事業主:▲57.1%
- 資本金2000万円未満の企業:▲42.0%
- 複数業種の建設業許可を受けている企業:54.0%で前年比微増
〈参考〉国土交通省ウエブサイト『全国の建設業許可業者は2年連続で増加〜令和6年度末の建設業許可業者数調査の結果〜』>調査結果(詳細)
労働者不足問題などをあわせて考慮すると、以下のような建設業者ほど企業経営が安定しやすく、建設業界の企業経営状態が2極化することをイメージできます。
【安定しやすい建設業者】
- 受注できる建設業種のバリエーションが多い
- 受注者の予算に応じて柔軟に対応可能
- 人口が安定している&予算が多い自治体で工事を請け負える
- 海外への営業地域拡大を検討できる
- 企業アピールの努力によって人材を獲得できる
- リピーターを獲得できる
- 建設業界以外の産業を兼業している など
建設業界で、プレゼンの段階から「より価値の高い品質提供の必要性」を感じている企業様は、株式会社MAKE HOUSEへお問い合わせください。
BIMを活用した建設業務の最適化を、提案・サポートいたします。
建設業界の中で今後10年で需要が高まる&安定し続ける業種
建設業許可の取得数が増加した主な業種は以下のとおりで、国内の社会情勢(保守管理需要増加、空き家増加など)と考え合わせても、今後10年間で需要が高まる&安定し続けることを予測できます。
- とび・土工工事業
- 解体工事業
- 内装工事業
〈参考〉国土交通省ウエブサイト『全国の建設業許可業者数は2年連続で増加〜令和6年度末の建設業許可業者数調査の結果〜』>調査結果(詳細)7ページ
また、建設業界の需要には以下のような特徴もあるため、選択する業種に応じて技術者の確保・建設業許可取得などの営業体制を整えるという視点も大切です。
- 公共工事の75%が土木工事
- 民間工事の84%が建築工事
〈参考〉国土交通省ウエブサイト『持続可能な建設業に向けた環境整備検討会』>参考資料1 最近の建設業を巡る状況について
まとめ
建設業界に対して、今後10年・20年といった長期的な視点での不安を抱えている方へ、建設業界の現状・実施されている取り組み・今後の動向予測などを解説してきました。
建設業界が変化していくことは確実ですが、建設業界が社会にとって必須の産業であることに変わりはありません。
今回紹介した情報を、今後の企業経営・建設業界での仕事選びなどに活用していただけると幸いです。