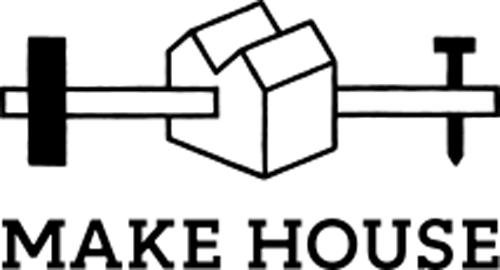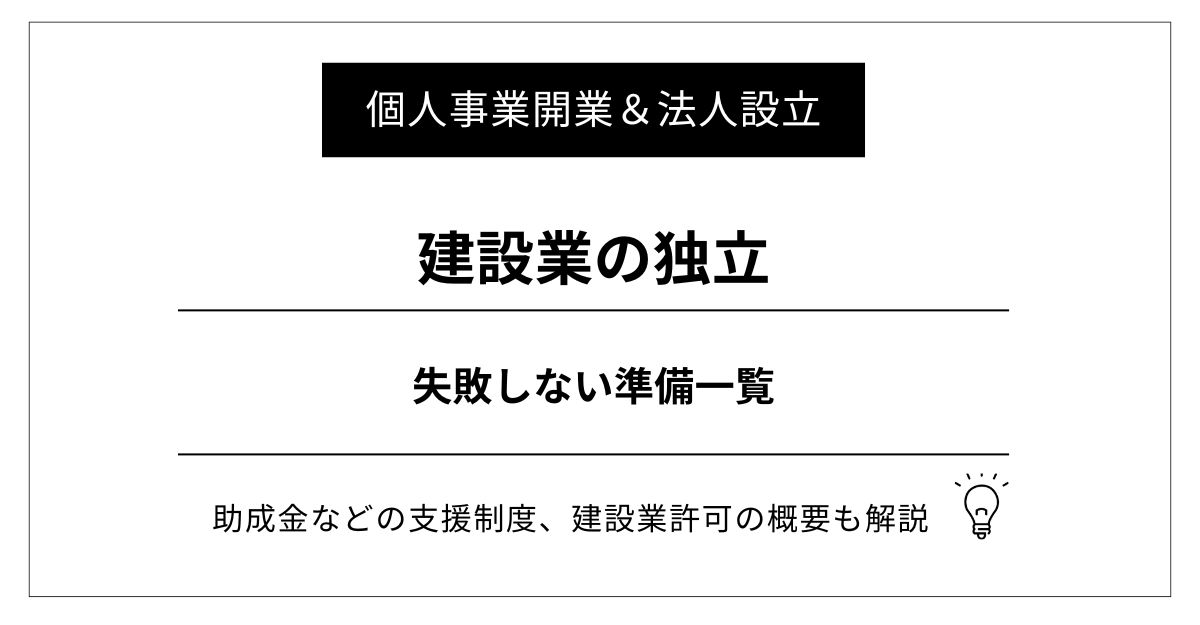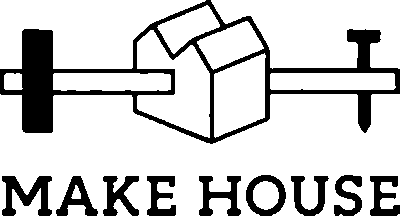建設業界で経験を積むと独立の道が見えてきますが、ご自身の業務経験のみに頼って独立すると、失敗する可能性があります。
「個人事業・一人親方」という選択をする場合であっても、経営者として、独立後の事業成功に必要な知識を身につけましょう。
今回は、BIM導入による建設業務の最適化をサポートしている『株式会社MAKE HOUSE』が、建設業の独立に必要な準備などを、わかりやすく解説します。
建設業界の中で、独立後も長く成長していく事業の土台をつくり出すために、ぜひ最後までごらんください。
「独立時の業務効率化に役立つITツールの導入を検討したい」とご希望の方は、『株式会社MAKE HOUSE』へお問い合わせください。
Contents
建設業の独立で失敗しない準備一覧

はじめに、建設業の独立で失敗しないために必須の準備を、確認しましょう。
準備不足で失敗する具体例も紹介するので、参考にしてください。
建設業の独立前にするべき準備一覧
建設業の独立前にするべき準備を、一覧表にまとめました。
| 準備 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 税務署へ書類提出 (税理士・会計士へ依頼も可能) ・設立届け(法人)、開業届け(個人) ・棚卸資産の評価方法の届出書 ・減価償却資産の評価方法の届出書 ・消費税関係の届出書 ・青色申告or白色申告を判断 →青色申告を選択する場合は書類提出 ・人材雇用をする場合は給与支払事務所の開設届 ・源泉所得税関係の届出書 |
◯ | ◯ |
| インボイス登録をする場合は税務署へ書類提出 | ◯ | |
| 法務局へ書類提出 (司法書士へ依頼も可能) ・設立登記 ・定款など必要書類を作成・提出 |
◯ | |
| 人材雇用をする場合の準備 (社会保険労務士へ依頼も可能) ・年金事務所などに健康保険・厚生年金保険の加入書類を提出※ ・公共職業安定所に労働保険の成立手続を提出 ・雇用契約書など雇用契約時に必要な書類を作成 |
◯ | ◯ |
| 建設業許可の取得を検討し、取得する場合は書類提出 (税理士・行政書士へ依頼も可能) |
||
| 士業の専門家に各専門業務の顧問を依頼するか検討 税理士・会計士、社会保険労務士など |
◯ | ◯ |
| 事務所を構え、備品をそろえる 建設業許可を取得する場合は事務所が必要 |
◯ | ◯ |
| 会計ソフトを選定し契約する (税理士・会計士に顧問を依頼する場合は相談可能〉 青色申告を選択する場合は会計ソフト利用が便利 |
◯ | ◯ |
| 建設業務に必要な車両・機械・道具などをそろえる |
◯ | ◯ |
| 事業用の銀行口座を作る 必要な場合は事業用のクレジットカードも作る |
||
| 資金調達 ・自己資金 ・金融機関などからの借り入れ |
◯ | ◯ |
| 事業計画・資金計画の策定 ・金融機関からの借り入れをする場合には必要 ・借り入れをしない場合でも策定がおすすめ ・創業支援センターや税理士に相談できる |
◯ | ◯ |
| 営業に必要なアイテムを用意する ・名刺 ・WEBサイト ・SNSアカウントなど |
◯ | ◯ |
※法人の場合、人材を雇用しない場合でも、役員が無報酬でなければ社会保険加入が必要です。
〈参考〉税務署への書類提出:国税庁『個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき』
建設業の独立で失敗する具体例

独立時の準備不足などが原因で失敗する具体例は、以下のとおりです。
- 営業努力をしたが仕事を獲得できない
- 経理方法・資金管理方法がわからず、資金不足となる・赤字になり資金調達ができない
- 人材雇用ができず、受注した仕事・経営者としての仕事・事務仕事をこなしきれない
- 価格・サービス内容で同業他社に勝てず、事業継続の意義を見失う など
既存の同業他社は、建築基準法などの法令・制度改正に応じて、サービスをブラッシュアップし続けています。
2025年の建築基準法の改正内容を、こちらの記事で確認できます。
▶おすすめ記事:「2025年改正建築基準法|重要ポイントをわかりやすく解説、懸念点解決策も」
独立後は事業全体を管理する必要がありますが、ご自身の時間は限られていますし、専門知識をお持ちではない分野もあると思います。
そのため独立準備の際には、「独立資金を有効活用する事業計画・資金計画」を検討してください。
- 人材雇用
- 建設作業用機械などの購入orリースの選択
- アウトソーシングサービスを利用
- ITツールを利用 など
次に、建設業の独立に必要な資金の目安も紹介するので、事業計画・資金計画の参考にしていただけると幸いです。
建設業の独立に必要な資金一覧|資金調達に役立つ助成金などの支援制度も紹介

建設業の独立時にはまとまった資金が必要ですが、助成金などの支援制度を活用すると、自己資金の支出を抑えられます。
「建設業の独立時に必要な資金の目安」「知っておくべき支援制度」などを、まとめて紹介します。
建設業の独立に必要な資金の目安一覧
建設業の独立に必要な資金額は、建設業種・営業体制などによって変動します。
建設業の独立時に必要な資金の目安を一覧表にまとめたので、参考にしてください。
| 準備 | 必要資金の目安 |
|---|---|
| 税務署へ提出する書類の作成・提出 | 0円〜3万円 |
| 法務局へ提出する書類の作成・提出 | 5〜20万円 |
| ・健康保険・厚生年金保険の加入書類作成・提出 ・労働保険の成立手続書類作成・提出 |
3〜10万円 |
| 建設業許可の取得 |
・申請手続き:20〜30万円 ・財産要件:自己資本500万円以上など |
| 税理士の顧問料 (月次決算+年次決算の依頼、税務相談など) |
・月次:1〜3万円 ・年次:5〜20万円 |
| 社会保険労務士の顧問料 (給与計算、労務相談など) |
2〜5万円 |
| ・事務所を構え、備品をそろえる ・建設業務に必要な車両・機械・道具などをそろえる ・市場調査費用 ・名刺作成・関係業者への挨拶など営業費用 ・人件費 |
適宜 |
| 会計ソフト利用料 | 数千円〜5万円/月 |
| WEBサイト・SNSなどオンラインマーケティングの費用 | ・制作:数万円〜100万円以上 ・運用:数千円〜10万円以上/月 |
※専門家に依頼する場合、内容が複雑になるほど・作業数が多くなるほど高額になるのが一般的です。また、上記は大まかな必要資金の目安であることを、ご了承ください。
独立をして個人事業開業・法人設立をする場合には、初めて売上を獲得する前の段階から経理処理が発生します。
(例)
- 資本金の計上
- 独立準備時に発生した費用の計上
- 借入金の計上 など
また、人材雇用をする場合には、売上を獲得できなくても人件費・源泉所得税・社会保険料などの支払いが発生します。
- 源泉所得税・住民税:事業者が給与から差し引いて預かり、納税する(毎月or半年毎)
- 社会保険料:事業者が給与から差し引いた分・事業者負担分を納付する(毎月) など
まとまった独立資金を準備できない場合には資金調達から始める必要があるため、次に独立時に活用できる助成金などの支援制度も紹介します。
独立資金の調達に役立つ助成金などの支援制度

独立資金の調達に役立つ支援制度は、以下のとおりです。
| 支援制度例 | 概要 |
|---|---|
| 助成金・補助金 | 【国】 ・持続化補助金 ・ものづくり補助金 ・IT補助金 など 【自治体】 自治体ごとに実施状況が違う |
| 創業融資 | 日本政策金融公庫などの金融機関・自治体が、低金利・無担保などの融資を提供 |
| 独立支援 | 各自治体・商工会議所が起業支援を実施していて、以下のような相談が可能 ・資金調達 ・事業計画の策定 ・関連業者紹介 など |
| 移住支援 | 各自治体が、移住と同時に起業する方の支援を実施しているケースがある ・移住支援金の交付 ・コワーキングオフィス提供 ・起業希望者向けイベント など |
〈参考〉国の助成金・補助金:経済産業省 ミラサポplus『人気の補助金』
ほかにも、「投資ファンドやエンジェル投資家からの投資を受ける」などの資金調達方法もあります。
独立費用を抑える方法
独立資金を有効活用するために、固定費を抑える方法を検討しましょう。
【固定費を抑える方法例】
- 人材雇用をせずアウトソーシング・外注・ITツールを活用:人件費・社会保険料などの負担を抑え、消費税の節税にもなる
- 資産になる機械などを購入せずリースを活用:減価償却費を抑え、赤字回避の対策になる
- 事務所ではなくレンタルオフィスを活用:毎月の賃料・備品購入費などを抑えられる。法人登記できるレンタルオフィスもある など
上記の中で特に「人材を雇用しない」という選択肢については、多数のサービスがあります。
- 営業
- 事務、秘書業務
- コールセンター など
また、建築業界で活用できるITツールの例として、BIMの注目度が高まっています。
BIM導入による建設業務の最適化サポートをご希望の方は、株式会社MAKE HOUSEへお問い合わせください。
ただし、外部サービスの利用には、必ずメリット・デメリットがあります。
常に費用とサービス内容のバランスを確認しながら、活用を検討してください。
建設業許可の概要を簡単解説|許可の要件、手続きなど

建設業の独立で失敗しないための準備を紹介してきましたが、ここで「建設業許可」について、「取得するべきかわからない」とお悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
建設業許可とは、「軽微な工事」以外の工事を受注するために必要な、建設業法上の許可のことです。
軽微な工事とは以下の工事のことで、独立後に受注する工事の規模によって、建設業許可は必須の許可となります。
- 建築工事一式:1,500万円未満
- 建築工事一式以外:500万円未満
独立と同時に建設業許可を取得するためには、以下のような要件を満たしたうえで、必要書類を指定機関(土木事務所など)に提出する必要があります。
【建設業許可を取得する要件】
- 経営業務の管理責任者がいる:建設業で経営業務管理責任者の経験5年など
- 建設業許可を受ける業種※に関して、専任技術者がいる:国家資格の有資格者など
- 誠実性を証明できる:工事請負契約に関して犯罪行為などの経歴がないなど
- 財産的基礎がある:一般建設業は資本金500万円以上、特定建設業は資本金2,000万円以上など
※建設業の業種は29種類です。
〈参考〉
・国土交通省ウェブサイト『許可申請の手続き』
・国土交通省ウェブサイト『関係通達』
また、建設業許可の有効期間は5年間で、許可を継続するためには、有効期間満了の30日前までに更新の手続きを実施する必要があります。
今回は建設業許可の概要を簡単に紹介しましたが、実際には詳細な要件があり、書類作成の内容も複雑です。
行政書士などの専門家に手続きを依頼することも可能なので、建設業許可の取得を検討する場合には、一度専門家へ相談してみることをおすすめします。
建設業の独立で失敗しないためのQ&A

最後に、建設業の独立に関するよくある疑問・回答を紹介します。
Q.売上を獲得しやすい建設業種を知りたい
A.確実に売上を獲得できる建設業種を提示するのは難しいのですが、以下の建設業種は建設業許可の取得数が増加しているため、需要が高い建設業種と言えます。
- とび・土工・コンクリート工事業
- 解体工事業
- 内装仕上工事業
売上を獲得しやすい建設業種・建設業界の今後の需要などを、こちらの記事で確認できます。
▶おすすめコラム:「建設業界は今後10年も必須産業|育成するべき人材、労働環境・技術革新・企業経営の将来性予測など」
Q.建設業で独立後の年収はどれくらい?
A.独立後の年収は、0円の方も1,000万円以上の方もいらっしゃいます。
理由は、事業の状態によって事業者の年収には大きな幅があるからです。
また、独立後は事業資金が不足した場合に自己資金を投入するケースもあり、年収と手元に残るお金が必ず一定のバランスになるとは言えません。
ただし、「原価率管理」「営業経費管理」「キャッシュフロー把握」に関心があり、一定の利益獲得を見通して経営をしている事業者は、安定した収入を確保している傾向があります。
Q.他業界から未経験で建設業を立ち上げることは可能?

A.他業界から未経験で建設業を立ち上げることは可能ですが、難易度は非常に高いのが現実です。
理由は、建設業界特有の仕入れ方法への順応・人脈を活用した営業などが難しいためです。
未経験での建設業立ち上げを検討する場合は、「M&Aなどである程度土台のある建設業者を購入する」といった選択肢も検討できます。
Q.個人事業開業or法人設立どちらを選ぶべき?
A.個人事業開業or法人設立の判断は、独立時の状況に応じて検討する必要があります。
「独立資金が限られている」「人材雇用をしない」「小規模な工事の受注から始める」といった場合には、小さな規模でスタートしやすい個人事業開業が向いている可能性があります。
「独立時に大きな額を借り入れしたい」「大規模な工事を受注したい」「源泉所得税などの節税対策をしたい」といった場合には、法人設立が向いている可能性があります。
税理士・会計士などの専門家に相談をして、アドバイスを受けることをおすすめします。
Q.独立後の営業に役立つツール・サービスを知りたい
A.独立直後は実績がないため、「他社と競合する場合のプレゼン資料」や「明確なサービス内容の提示」が、売上獲得のカギとなります。
(例)
- プレゼン資料で立体的なイメージを提示できる3Dパース・動画を、BIMで作成
- 見込み客が営業内容を気軽に確認できるWEBサイト・SNSなどを運用 など
一人親方が効率的に営業するためのツール・サービスも多数あるので、ぜひIT活用の知識を持つ専門家に相談し、営業戦略の情報交換が可能な人脈を広げて下さい。
BIMを活用した営業方法の相談先をお探しの方は、株式会社MAKE HOUSEへお問い合わせください。
まとめ
建設業の独立で失敗しないために、必須の準備・必要資金など、確認しておいていただきたい情報を紹介してきました。
建設業務・経営業務を両立するために、独立時には事業全体の業務に興味を持って知識を習得する必要があります。
ぜひ今回紹介した情報を参考に、外部の専門家や便利なツールを活用して、独立までのステップをスムーズにクリアしていただけると幸いです。
こちらの記事で、業務を効率化する方法を具体的に確認できます。
▶おすすめ記事:「施工の合理化に役立つVEとは|中小建築業者が健全なコスト削減&工期短縮を目指す具体的な方法を簡単解説」